
建築家全員が総力を上げて手掛ける、
五感に響くオンリーワンな邸宅
小堀住研
一生に一度の大きな買い物といえるマイホーム。できるのであれば、予算の枠にとらわれず、注文住宅で隅々まで納得のいく家づくりを進めたいもの。そこで今回は、企業建築家集団として数多くの家づくりを手掛けてきた小堀住研に訪問し、法人事業部の佐野亮平さんにインタビューを実施。同社の特色である質を重視した提案を行うための体制や、競合となる設計事務所やハウスメーカーと比較した際の特色などを中心に、普段はあまり語られることのないデメリットとなる部分についてもお話を伺い、実際の建築事例も3邸紹介いただいた。
目次
- 小堀住研の実際に建てられたユーザーを紹介
- 邸宅実例Ⅰ:自慢のカーコレクションを身近に感じながら暮らせるミュージアムのようなガレージハウス
- 扇状に並べたガレージに一目ぼれ
- 車の見え方と距離感を重視
- 友人たちからも「ショールーム以上」との評価
- 邸宅実例Ⅱ:高級住宅街に馴染む景観の自宅とノスタルジックな雰囲気の貸別荘
- 歴史ある町並みを継承する邸宅
- ゲストと語らう別荘
- 邸宅実例Ⅲ:不整形な敷地形状を活かし、借景を取り入れた邸宅
- 敷地形状を活かし切る提案力が決め手に
- クセのある土地は考え方次第でポジティブになる
- 小堀住研の高級住宅・邸宅へのこだわり・コンセプト
- 小堀住研の高級住宅の特徴
- 小堀住研の不得意なところ
- 小堀住研の会社概要・基本情報
- プランのお問い合わせ先について
取材先情報

株式会社ヤマダホームズ
法人事業部 東京
佐野 亮平さん
入社12年目(取材時)。現在に至るまで、お客様からの様々なご要望に応え、高いクオリティーの住宅提案を行っている。
CASE
小堀住研の
邸宅実例3選
安心感ある施工体制のなか、デザインにとことんこだわった家づくりができることで定評のある小堀住研。その自由度の高さを生かして建てられた邸宅の実例を3邸ご紹介。いずれも建売住宅などではまずみられない、個性の際立つ家々ばかりだ。
邸宅実例 Ⅰ
自慢のカーコレクションを
身近に感じながら暮らせる
ミュージアムのような
ガレージハウス

【埼玉県の邸宅】
構造:木造
土地面積:約1,614㎡(約489坪)
延床面積:約287㎡(約87坪)

扇状に並べたガレージに
一目ぼれ
オーナーは多数の自動車を所有するカーコレクター。別々の場所で管理していた愛車を一堂に集めて暮らせるガレージハウスの計画である。小堀住研が提案したのは扇を広げたようにゆるやかなカーブを描く住まい。扇状にすることでガレージに並んだ愛車を端から端まで一望できるというユニークな提案を気に入り、小堀住研を家づくりのパートナーに選んだ。当初の建築地で進められなくなるトラブルもあったが、新たに施主自らがこのプランを実現できる土地を探して建築が進められた。

車の見え方と距離感を重視
扇状の建物の外側から中心に向かって、車路、ガレージスペース、居住スペースと並ぶ平面計画で、家中どこにいても愛車を眺めることができる。扇型の形状は、並べられた愛車を少しずつ角度を変えながら楽しめることに繋がり、ロフトに登ると俯瞰的な眺めも楽しむこともできる作りだ。
扇形であるが故に構造や窓の納め方などに頭を悩ませたが、オーナーの想い以上のものを具現化できる仕上がりとなった。
この計画には続きがあり、庭の一画に別棟のガレージを増築した。当初の予定よりも広い敷地を手に入れたことで可能になったこのガレージもまた、ショールームのように、愛車を保管するだけではなく眺めたり入れ替えたりを楽しめる作りになっている。

友人たちからも「ショールーム以上」との評価
竣工を祝い、自動車愛好家の仲間たちを呼んで内覧会を開催した。ゲストからは「ショールーム以上だね」との言葉をもらったそう。今は車愛好家たちの輪を広げられる憩いの場となっているとのことだ。
邸宅実例 Ⅱ
高級住宅街に馴染む景観の自宅と
ノスタルジックな雰囲気の
貸別荘

【東京都の邸宅】
構造:木造
土地面積:約691㎡(約209坪)
延床面積:約278㎡(約84坪)

【北海道のゲストハウス】
構造:木造
土地面積:約3,423㎡(約1,035坪)
延床面積:約466㎡(約140坪)

歴史ある町並みを継承する邸宅
敷地は歴史ある住宅地にあり、オーナーは幼少の頃からこの町並みと共に暮らしてきた。近年は住み手の変化により歴史ある景観が失われ始めており、町並みの継承が計画のテーマとなった。
大谷石積みの塀や既存の樹木をできる限りいかすことで、プライバシーを保ちながら大きな開口部を設けて庭や採光、通風を楽しめる設計となっている。「過去や伝統をいかし現代と調和させる」ことで新しい価値を生み出す、小堀住研の姿勢が垣間見える。

ゲストと語らう別荘
自邸で小堀住研の提案を評価された施主は、続いて北海道に建てる別荘を依頼。
北海道らしい雄大な風景の中にある敷地で、今度は、サイロやギャンブレル屋根の農家、石積みの蔵や木造駅舎といったこの地に古くからある建築様式を拠り所に環境との調和を図った。
パノラマビューのラウンジから始まり、部屋ごとに内装や景色が異なる客室など、来た人が楽しめる工夫を凝らした別荘で、ゲストを招き語らう暮らしを夢に見るオーナーの期待に応える一邸に仕上がった。
邸宅実例 Ⅲ
不整形な敷地形状を活かし、
借景を取り入れた邸宅

【東京都の邸宅】
構造:RC造
土地面積:約165m2(約50坪)
延床面積:約278m2(約84坪)

敷地形状を活かし切る提案力が
決め手に
都内有数の邸宅地に建築された事例として、RC造の住まいをご紹介する。
計画地は、居住者専用の私道を進んだ突き当たりにふと現れる。車の回転スペースに縁取られた円弧状の道路境界線と、マンションとゲストハウスの庭園に挟まれた平行四辺形を組み合わせたような特殊な形状で、矩形の建物では残地が多く残り有効な床面積が小さくなってしまうことが懸念された。
そこでRC造の特性を活かし、敷地の外郭形状をなぞるような建物形状、かつゲストハウスの庭園側に大きな開口を設けるプランを提案した。

クセのある土地は
考え方次第でポジティブになる
他社が矩形の建物を提案する中、敷地の条件を素直に受け止めプランニングすることで、造形的な外観とそこにしかない緑豊かな内部空間が生まれた。
玄関を入った瞬間に見える緑や、弧を描く吹き抜けを持つ開放的なリビング、家のどこにいても借景を感じられるゾーニングは、まさにこの敷地条件を深く読み解き導き出した最適解だと言える。
傾斜地や変形地など特殊な条件にある土地を制約としてネガティブに受け取るのではなく、ポジティブにどう活かすかを考える小堀住研の個性が発揮された一例だといえるだろう。
CONCEPT
小堀住研の
高級住宅・邸宅への
こだわり・コンセプト
小堀住研は、ヤマダホームズの中にあるこだわりのオンリーワンの家に特化した企業建築家ブランド。創業は1951年と、70年以上の歴史があり、構造や工法にとらわれない家づくりを手掛けている。
創業者の小堀林衛が掲げた「住まいの哲学」を礎に、伝統と現代の風潮を調和させながら、機能だけでなく感覚も重視した家づくりを追及。
「理想、の先へ」を理念に掲げ、1邸1邸、担当する1人の建築家のみの視点ではなく、企業として、所属する建築家全員でブラッシュアップを行い、施主の理想を超えた住まいを提供することにこだわっている。



1邸1邸、総力を集結して提案

佐野さん:
小堀住研は少数精鋭の集団であり、量より質を重視した家づくりを旨としています。お客様との対話から理想やお困りごとを探る『プランインタビュー』を経て、プランをご提案する前には『デザインレビュー』を実施。担当設計者が作成したプランについて、お客様の理想を満たすだけでなく、より良い提案ができているかどうかを所属するメンバー全員で多角的に検証しています。お客様との接点として担当チームはありますが、意識としては組織一丸となって取り組んでいる感覚です。そのため、ご提案までのお時間は他社よりも長くいただくかもしれませんが、ファーストプランのまま大きな修正もなく進むケースがほとんどです。
設計事務所とハウスメーカーの
メリットを兼備

佐野さん:
自由度の高い設計が行えるということで設計事務所が競合となるケースがあります。この場合、弊社はハウスメーカーでありますので、企業として設計から施工、アフターメンテナンスまで一貫した体制で対応できる点で差別化ができ、選んでいただける決め手になります。逆にハウスメーカーが競合となる場合は、他社にはない発想やそれらを実現できる力が決め手になります。
いわゆる標準仕様というものがなく、お客様ひとりひとりに合わせた提案ができるので、こだわって住まいづくりをしたいというお客様には向いていると思います。
対話によって実現する、
五感に響く家づくり
近年、UA値やC値など家の快適性に関わる数値がたくさんありますが、一方で快適性には風の通りや光の入り方、目線の抜けといった数値に表れない感覚的な部分もあります。小堀住研は創業当初からそういった五感に訴える住まいづくりを大事にしてきました。お客様ごとに多様な価値観を持っていらっしゃいますので、それを敏感に察知するためにお客様との『対話』を重ねて、どうしたらお客様の想像以上に喜んでいただけるかを常に考えています。またお客様だけでなくチーム内や施工会社など家づくりに関わる全ての人に『対話』を通じてそれを伝えることも重要です。
FEATURES
小堀住研の
特徴
注文住宅の醍醐味の1つ「自由設計」の範囲の広さで高い評価を得ている小堀住研。その自由度以外にも、さまざまな面で個性や特色がみられる。
小堀住研の外観・内装デザインの特徴

佐野さん:
「『こういったデザインが得意』というものは特になく、1邸1邸お客様がどういった点にこだわっているのか、何を大事にしているのかを突き詰めて提案するのが、私たちの姿勢です。そのため、ファーストプランの提案前には必ず『デザインレビュー』というプロセスを踏んでおります。担当する設計士だけでなく、小堀住研に所属する他の設計士たちの目で、お客様の理想以上の提案になっているかを検証するもので、ほかのハウスメーカーだけでなく、設計事務所とも差別化できるポイントになっているかと思います。広い視野で様々な視点から、ベストの提案になっているかをチェックする非常に重要なステップとなっています。」
小堀住研の間取り設計の特徴
佐野さん:
「構造についても得意分野や独自のこだわりといったものはなく、ご提案に合わせて適したものを選ぶようにしています。この、プランや要望、敷地条件、予算に合わせて構造を切り替えているという点が強いていえば特徴となるでしょうか。様々な構造を取り扱うからこそ、それぞれの強味を理解して提案できるのが強味ですね。」
小堀住研の住宅設備・性能の特徴

佐野さん:
「設備面についてですが、小堀住研ではいわゆる標準仕様というものがございません。お客様の好みをヒアリングして、ご提案しております。これまでどのようなライフタイルを歩んできたか、これからはどのようなライフスタイルを望んでいるのかなど、しっかりと対話を重ねて、使い勝手・デザインなどを加味した製品を提案致します。国内製に限らず、海外製を取り入れることもあり、お客様と一緒にショールームを回って、探すこともありますね。」
WEAK POINT
小堀住研の
苦手とするところ
小堀住研でのデメリットを挙げるとすれば、『時間』と『エリア』の2点になるだろう。
少数精鋭という点と、理想を超える提案をするための『デザインレビュー』を実施していることから、最初のプランを提出するまでに少なくとも1か月は要する。
タイミングや規模によってはそれ以上にお待たせしてしまうこともあるとのこと。
一方、対応できるエリアについては、設計監理やアフターメンテナンスなどの対応をしっかり行うため、イレギュラーはあるものの基本は関東圏・関西圏に絞られている。
小堀住研の
会社概要・基本情報
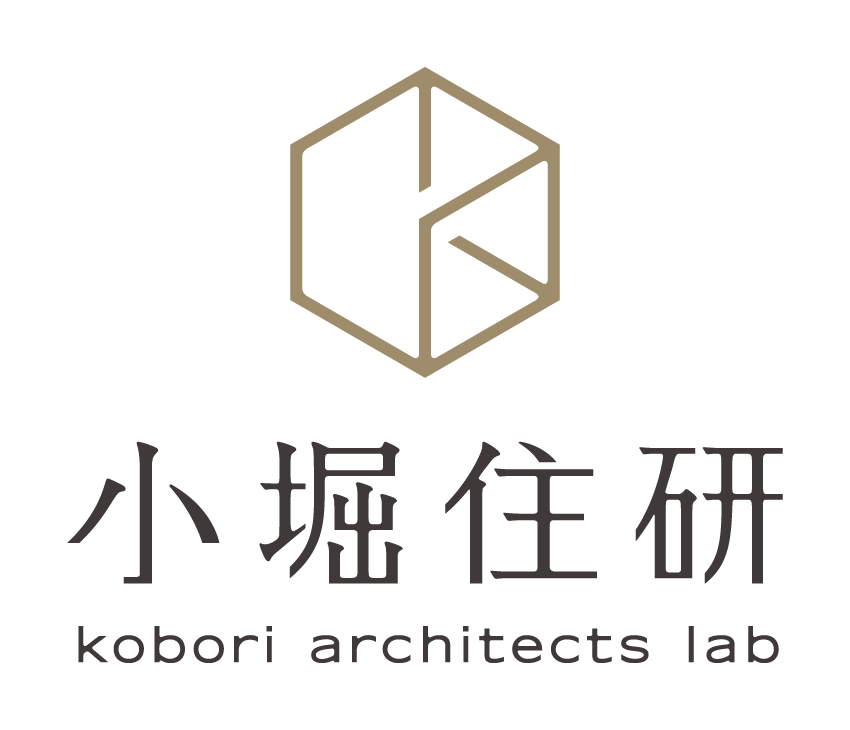
Request for Planning
プラン作成サービス
ご利用の流れ

1
希望条件を
フォーム入力

2
建築会社との
日程調整

3
展示場または
オンラインで商談

4
依頼先を
決定・契約
GALLERY
小堀住研の高級住宅建築実例


















Contents
小堀住研に関する記事
家づくりのとびらプレミアムで、
最高の建築会社選びを

希望条件の整理や、会社への申し送りなどのコーディネーターによるサポートも充実。
厳選された、高級注文住宅の実績豊富な企業から、あなたのこだわりを叶える会社が見つかります。
