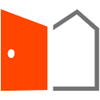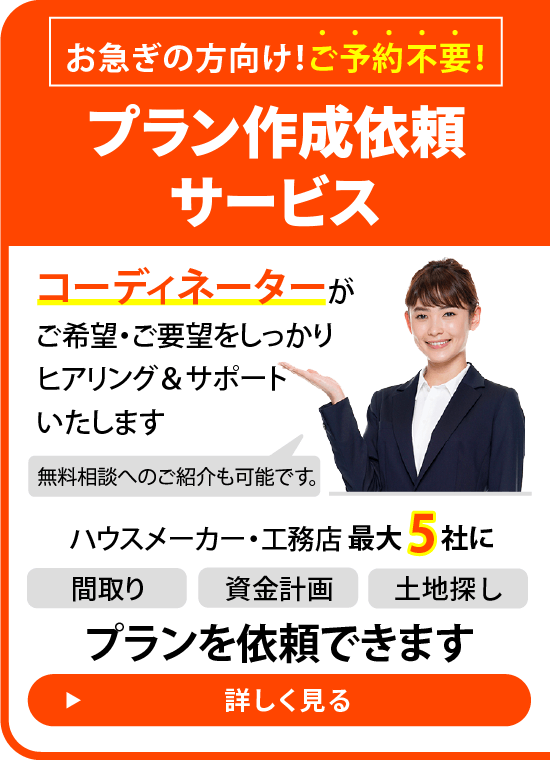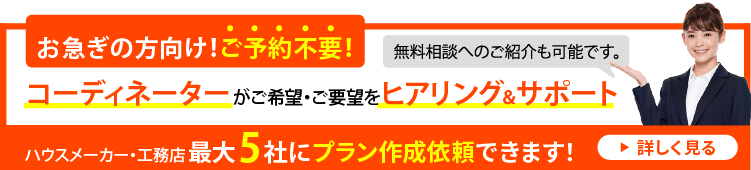- 変更日:
- 2026.02.04
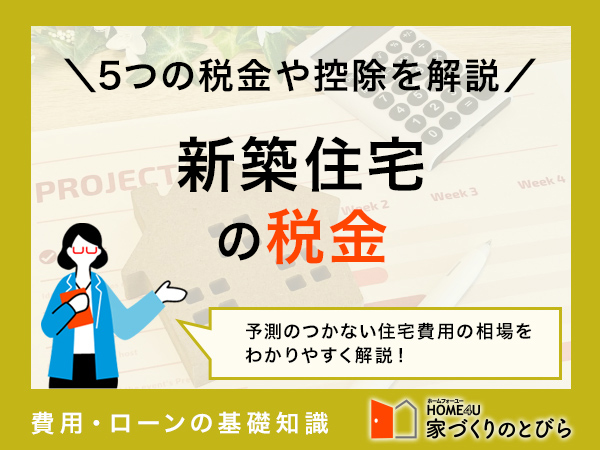
注文住宅を建てたり、新築一戸建てを購入したりするときに、気になるのが税金ですよね。
家を新築する際、例えば土地・建物合わせて5,000万円の家の場合、最初に一度だけ負担する税金が約29万円、毎年かかる税金が約16万円かかります(実際の税額は諸条件によって異なります)。
購入後は毎年の固定資産税や都市計画税の納税等も必要です。
新築住宅では主に5種類の税金が課税されますが、還元される税金もあります。
| 名称 | いくら? | いつ支払う? |
|---|---|---|
| 印紙税 | 例)1,000万円超5,000万円以下なら2万円(軽減制度適用なら1万円) | 売買契約時、建築請負契約時、住宅ローンの契約時 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4%~2%(軽減制度あり) | 引き渡し日(登記するとき) |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額×3%(住宅の場合) | 家を建ててから半年~1年後に納付書が届く |
| 名称 | いくら? | いつ支払う? |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 評価額×1.4%(軽減制度あり) | 建物は新築の翌年から。4~6月頃に納付書が届く |
| 都市計画税 | 評価額×0.3%(軽減制度あり) | 固定資産税と同時 |
| 名称 | いくら? | どんな手続き? |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除(減税) | 住宅ローン年末残高に応じて13年間(または10年間)所得税から控除。住民税からも一部控除 | 初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で可能 |
新築住宅の税金をしっかりと把握しておかないと、建築費以外にかかる諸費用の支払いに困ったり、住宅ローンの返済計画も想像よりも厳しくなったりしてしまいます。
マイホームを建てる前に、本記事を参考に現実的な資金計画を立てる準備をしておきましょう。
無料

まとめて依頼

注文住宅にかかる費用内訳の全体像が知りたい方は「注文住宅の費用内訳」の記事もご覧ください。

柴田 充輝
FP1級技能士・社会保険労務士・行政書士・宅建士。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じ、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に1,000記事以上を執筆。
目次
1.新築一戸建ての購入時にかかる税金は3種類
購入するときにかかる主な税金は、「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」の3種類です。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
1-1.印紙税
印紙税は、特定の契約書を作成するときにかかる税金です。
収入印紙を契約書に貼付し、消印して納税します。
【納税のタイミング】
次の契約書を作成するときに印紙税が必要です。
- 売買契約書:土地の売買契約、あるいは完成した建売住宅について土地・建物の売買契約を結ぶ契約書。
- 建築請負契約書:ハウスメーカーや工務店と結ぶ注文住宅を建築するための契約書。
- 住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約):金融機関と結ぶ住宅ローンに関する契約書。
【税額】
契約書に記載された金額に応じて税額が決まります。
| 契約金額 | 通常 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
【軽減措置】
不動産(土地・建物)の売買契約書と新築工事の請負契約書の印紙税については、2027(令和9)年3月末まで上記のとおり軽減措置が適用されます。
1-2.登録免許税
登録免許税は、登記の手続きの際に発生する税金です。
金融機関で納税して領収証書を登記申請書に貼付するか、納税額3万円以下であれば収入印紙を登記申請書に貼付します。
【納税のタイミング】
建物や土地の所有権が移って自分の所有になる際、引渡し日に法務局で登記を行うタイミングで登録免許税を納税します。
住宅ローンを利用して住宅を購入する際は、抵当権の設定登記の際に登録免許税がかかります。
【税額】
税額は下記の通りです。
所有権保存:固定資産税評価額×0.4%
所有権移転:建物は固定資産税評価額×2%、土地は固定資産税評価額×2%
抵当権設定:債権金額×0.4%
【軽減制度】
一定の条件を満たした場合、軽減制度により下記の通りに減税されます(適用期限は2027年3月31日まで)。
所有権保存:住宅は0.15%に軽減(認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は0.1%)
所有権移転:建物部分は0.3%に軽減(認定長期優良住宅のマンションは0.1%、戸建ては0.2%、認定低炭素住宅は0.1%)
抵当権設定:住宅は0.1%に軽減
軽減措置を受けるための条件は、床面積が50平米以上であること、住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けることなどです。
住宅の登記に関する軽減措置を受けるためには、登記申請の際に市町村等の証明書の添付が必要です。
登記の手続きは司法書士に依頼するケースが多く、登録免許税の税額などは事前に教えてもらえます。
1-3.不動産取得税
不動産を新たに購入したり、家を建てたりしたときに課税されるのが不動産取得税です。
毎年の課税ではなく、取得した際の一度だけの課税となります。
【納税のタイミング】
土地や建物の引き渡しの数ヶ月後に行政から納付書が届きます。
納付書が届くまで1年以上かかるケースもあり、時間がたってから納税するので、納税資金を忘れないように準備しておきましょう。
【税額】
不動産取得税は、固定資産税評価額×税率で計算できます。
税額は原則4%です。
【軽減制度】
- 宅地や住宅への軽減制度
- 税額は原則4%ですが、住宅の場合は評価額×3%に軽減されています。
また、宅地の評価額は2分の1になる特例措置が適用されます(適用期限は2027年3月31日まで)。 - 新築住宅の軽減措置
新築住宅の場合、建物の延べ床面積が50平米(約15.1坪)以上・240平米(約72.6坪)以下であれば、1,200万円の控除が受けられます。
長期優良住宅なら1,300万円に優遇が拡大されます。
一戸建ての建物部分の評価額が1,200万円を超えない場合も多いため、その場合は不動産取得税がかかりません。
なお、適用期限は2026年3月31日までです。
- 新築住宅を建てた敷地の軽減措置
- 土地も、一定の条件を満たしていれば軽減措置を受けることができます。
軽減措置を受けた場合の不動産取得税額の計算式は以下の通りです。
土地の不動産取得税額=((土地の固定資産税評価額×1/2)× 3%)– 軽減額
計算式の中にある「軽減額」は下記の2つのうち、金額の大きい方が適用されます。
- 45,000円(税額45,000円未満はその金額)
- (土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積×2(200平米まで)×税率3%
新築住宅の場合、軽減措置を適用することで、不動産取得税が0円になることもあります。ただし、「新築住宅の軽減」や「住宅地の軽減」を受けるためには申請が必要です。
このように、家を建てる際にはさまざまな税金がかかります。
家づくりを検討しだしたら、まずは無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスをご利用ください。
スマホやパソコンから簡単にあなたの予算に合ったハウスメーカー・工務店がわかるうえ、実際の住宅プラン(資金計画含む)を複数比較することができます。
ハウスメーカー・工務店があなたのために作成した住宅プランの費用がわかるため、無理のない資金計画を立てやすくなりますよ。
家づくりのとびらコラム
新築費用に消費税はかかる?
住宅を購入するとき、消費税は建物だけに課税され、土地にはかかりません。
注文住宅の場合、ハウスメーカーや工務店に支払う建築費に対して10%の消費税がかかります。
設計料がかかる場合には、これも課税対象です。
建売住宅の場合は、消費税込みの総額の価格が表示されますが、建物部分だけが課税対象となっています。
そのため、売買契約書に土地代金と建物代金の内訳が記載されていないときには、消費税から逆算すれば建物価格がわかります。
また、土地の売買で不動産会社を経由する場合は、仲介手数料にも消費税がかかります。

柴田 充輝
電子契約の場合は印紙税が不要となるため、ハウスメーカーによっては電子契約を採用している場合があります。契約前に確認しておきましょう。
登録免許税の軽減措置適用には床面積50平米以上という条件があります。住宅によっては要件を満たさない場合があるため、設計段階での確認が必要です。
不動産取得税は納付書が1年後に届くことがあり、存在を忘れがちな税金です。新築住宅では軽減措置により課税されないケースが多いものの、高額物件や豪華仕様の場合は課税される可能性があります。
引渡し後も10万~20万円程度の予備資金を確保しておくことをおすすめします。
2.マイホーム建築後に毎年かかる税金は2種類
住宅を購入後、所有している期間にかかる税金は固定資産税と都市計画税の2種類です。
一般的に、一戸建てに毎年かかる固定資産税・都市計画税は合わせて10万~15万円くらいが平均といわれています。
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
2-1.固定資産税
【納税のタイミング】
原則として毎年1月1日時点で固定資産(土地や家屋など)を所有している人が課税対象です。
毎年4~6月頃に納税通知書が市町村から届き、記載されている税額を支払います。
納税方法は一括納付か、年に4回の分割納付にする方法があります。
【税額】
固定資産税の計算方法は下記の通りです。
固定資産税=評価額×税率(1.4%程度)
ほとんどの自治体で税率は1.4%です。
建物の評価額は、築年数が経つにつれて下がっていきます。
土地の評価額は地価の変動があればそれに伴って変わることがありますが、実勢価格(市場の売買価格)の70%程度になっています。
【軽減制度・優遇制度】
- 住宅用地の特例措置
住宅用地については、以下のように特例措置によって税負担が軽減されています。
地積 減額 小規模住宅用地(200平米(約60.5坪)まで) 6分の1 一般住宅用地(200平米を超える) 3分の1 適用期限は、2027(令和9)年3月31日までです。
- 新築住宅の減額制度
新築住宅(床面積120平米までが条件)であれば新築後3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
認定長期優良住宅の場合は新築後5年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
適用期限は、2026(令和8)年3月31日までです。
住宅用地とは異なるためご注意ください。
2-2.都市計画税
【納税のタイミング】
都市計画税は、市町村が都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てるための税金です。
ただし、市街化調整区域の場合は都市計画税は課税されません。
固定資産税と同様に、1月1日時点の不動産の所有者に課税され、都市計画税は固定資産税と合わせて納付書が送られてきます。
【税額】
都市計画税の計算方法は下記の通りです。
都市計画税=評価額×税率(最高税率0.3%)
税率は市町村によって異なりますが、最高で0.3%までと決められています。
【軽減制度・優遇制度】
住宅の敷地については、以下のような軽減制度があります。
| 地積 | 減額 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200平米(約60.5坪)まで) | 3分の1 |
| 一般住宅用地(200平米を超える) | 3分の2 |
適用期限は、2027(令和9)年3月31日までです。

柴田 充輝
固定資産税と都市計画税の総額は、立地により大きく変動します。都心部と地方部では、10万円以上の差が出ることも珍しくありません。
市街化調整区域では都市計画税のコストを抑えられますが、市街化調整区域は建築制限があります。希望通りのマイホームを建てられない可能性があるため、利便性とのバランスを考慮しましょう。
資金計画を立てる際に大事なのは、自分が建てようとしている家はいくらくらいかかるのかを把握しておくこと。
まずは無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスをご利用ください。
ハウスメーカー・工務店があなたのために作成した住宅プランの費用がわかるうえ、疑問点やお悩みが出た際には、コーディネーターや注文住宅のプロに無料で相談することもできます。
営業トークは一切ないので、ぜひお気軽にご利用ください!
3.所得税が戻ってくる「住宅ローン控除(減税)」
この章では、税金が戻ってくる「住宅ローン控除(住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除)」の制度についてご紹介します。
参考:国土交通省「住宅ローン減税」「 住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税・個人住民税)」/国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税・個人住民税)」/国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
3-1.住宅ローン控除の仕組み
一戸建てを新築すると、多くの方が住宅ローンを利用します。
住宅ローンを利用した方は、一定の条件をクリアすると「住宅ローン控除」を利用できます。
2025年における、住宅ローン控除の借入限度額は以下のとおりです。
| 住宅種類 | 一般世帯 | 子育て・若者夫婦世帯 |
|---|---|---|
| 固長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
| その他の住宅 | 0円(※) | 0円(※) |
※「その他の住宅」は、2023年末までに新築の建築確認を受けた場合のみ2,000万円が上限。
住宅ローン控除は、より多くの人が住宅を取得しやすいように、住宅ローンを利用する際に支払う金利の負担を減らすことを目的とした減税制度です。
最長で13年間にわたって、居住開始後の年末借入残高の0.7%が取得税と住民税から減税されます(住民税から減税できる金額には上限あり)。
▶理想の条件を押さえた家づくり、最適価格を知る方法(無料)3-2.住宅ローン控除を受ける適用条件
2024年の改正により、住宅ローン控除は以下のような「環境性能の高い住宅」のみが適用対象となりました。
対象の住宅
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素住宅
- ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅
- 省エネ基準適合住宅
- その他の住宅(上記以外)
ただし、2023年12月31日までに新築の建築確認を受けている場合は、その他の住宅でも適用されます。
逆にいえば、2024年以降に建築確認を受けた「その他の住宅」は、住宅ローン減税の対象外です。
また、住宅ローン控除を受けるためには次のような条件を満たす必要があります。
住宅ローン控除を受けるための条件
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
- 住宅ローン控除を申請するご自身が居住していること。
- 建物に関しては、床面積が50平米以上であること、居住用の割合が1/2以上であること。
3-3.還付される税額と期間
控除額と期間は、入居の時期や新築した住宅の性能によって異なります。
また、過去の住宅ローン控除の期間は10年でしたが、現在の還付期間は13年に延長されています。
環境性能の高い住宅ではく、2023年12月31日までに新築の建築確認を受けている場合、還付期間は最大10年になります。
2024年度から借入限度額が引き下げられる予定でしたが、子育て世帯※1と若者夫婦世帯※2に関しては据え置きとなりました。
※1…19歳未満の子を有する世帯
※2…夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
3-4.住宅ローン控除を利用する方法
住宅ローン控除を受ける最初の年、は確定申告が必要です。入居した年の翌年に、確定申告を行いましょう。
2年目以降は、会社員や公務員であれば年末調整で減税を受けられます。勤務先に対して、所定の書類を提出しましょう。
なお、自営業者の方が住宅ローン控除を受けるためには、毎年確定申告が必要です。
住宅ローン控除はとてもお得な制度なので、必ず適用条件や利用方法を確認しておきましょう。
▶理想の条件を押さえた家づくり、最適価格を知る方法(無料)3-5.住宅ローン控除と併用できる特例措置
住宅ローン控除と「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は併用できます。
この特例は、マイホームを買い替えるときに譲渡損失が生じた場合、その年の給与所得や事業所得などの他の所得から控除できる特例です。
主な要件は、以下のとおりです。
特例の適用を受けるための主な要件
- 売却したマイホームが国内にあり、居住用として使用していたこと
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
- 売却後、一定期間内に新たなマイホームを購入し、実際に居住すること
- 新しいマイホームの取得に住宅ローン(返済期間10年以上)を利用していること
参考:国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」/公益社団法人全日本不動産協会「居住用不動産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」
損失が大きく、1年で控除しきれないときは、翌年以後3年内にわたって損失を繰り越して控除できます。
住宅ローン控除と組み合わせることで、さらに所得税額を減額できることがあります。要件に該当する場合は、忘れずに確定申告の際に申告しましょう。
一方、次の特例措置は住宅ローン控除とは併用できません。
住宅ローン控除と併用できない特例一例
- 3,000万円の特別控除
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換え特例
上記のいずれかの特例措置の適用条件を満たす場合は、住宅ローン控除とどちらを利用するほうがよいかシミュレーションしてみましょう。

柴田 充輝
2024年以降の制度変更により、省エネ性能のない「その他の住宅」は原則として住宅ローン控除の対象外となりました。
ただし、2023年末までに建築確認を受けた物件は適用されるため、中古住宅や建売住宅を検討する際は建築確認の時期を必ず確認しましょう。
子育て世帯・若者夫婦世帯は、借入限度額が優遇されるため、より大きな節税メリットを感じられるでしょう。
例えば、長期優良住宅なら一般世帯の4,500万円から5,000万円に借入限度額が拡大されるため、年間最大で3.5万円(500万円×0.7%)の減税効果の差が生まれます。
4.マイホーム新築時の税金シミュレーション
家を建てたらかかる税金についてさらに具体的にわかるように、シミュレーションをしてみました。
以下の条件で税金を計算してみます。
【条件】
- 土地の売買価格1,500万円、建物を3,500万円で新築(合計5,000万円)。
- 土地を購入して3年以内に長期優良住宅を建築。2025年入居。
- 土地の固定資産税評価額1,000万円、建物の固定資産税評価額1,300万円。(土地140平米、建物100平米)
- 住宅ローン借入額は5000万円。
4-1.【家を建てたときに一度だけ負担する税金 】
| 税金 | 税額 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 40,000円 | 土地の売買契約:1万円 建物の工事請負契約:1万円 住宅ローン契約:2万円 |
| 登録免許税 | 219,500円 | 土地の所有権移転登記 1,000万円×1.5%=150,000円 建物の所有権保存登記 1,300万円×0.15%=19,500円 抵当権設定登記 5,000万円×0.1%=50,000円 |
| 不動産取得税 | 30,000円 | 土地 (1,000万円×2分の1×3%)-214,285円 < 0円 → 0円 ※土地の軽減額1,000万円×1/2÷140平米×200×3%=214,285円 建物 (1,300万円-1,200万円)×3%=30,000円 |
| 合計 | 289,500円 |
4-2.【毎年かかる税金 】
| 税金 | 税額 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 約114,000円 | 土地 1,000万円×6分の1×1.4%=約23,000円 建物 1,300万円×2分の1×1.4%=91,000円(3年間は2分の1に軽減) |
| 都市計画税 | 約49,000円 | 土地 1,000万円×3分の1×0.3%=約1万円 建物 1,300万円×0.3%=39,000円 |
| 合計 | 約163,000円 |
注意:各税金は2025年7月現在の税制を基準に計算しているため、税額は変動する可能性があります。
4-3.【戻って来る税金 】
子育て世帯・若者夫婦世帯が長期優良住宅を建てた場合
長期優良住宅に適用される借入限度額は4,500万円です(子育て・若者夫婦世帯は5,000万円)。
5,000万円×0.7%=1年間の最大控除額35万円
13年間の最大控除合計額は、35万円×10年=455万円です(「納めた所得税+住民税9.75万円」が35万円未満の場合、上記のメリットを上限まで受けられないことがあります)。
子育て世帯・若者夫婦世帯以外が長期優良住宅を建てた場合、借入限度額は4,500万円です。
子育て世帯・若者夫婦世帯以外が長期優良住宅を建てた場合
4,500万円×0.7%=1年当たりの最大控除額31.5万円
31.5万円×13年=13年間の最大控除額409.5万円
このように、住宅ローン控除はまとまった金額が戻ってくることが多いため、ローン控除で還付された税金を使って固定資産税を納税する方も多くみられます。
また、住宅の将来のメンテナンス費用として積み立てていくのもおすすめです。

柴田 充輝
子育て・若者夫婦世帯なら、13年間で最大455万円の減税効果があり、これは初期の税負担を大幅に上回るでしょう。
ただし、実際には返済が進むにつれて残債が減るため、住宅ローン控除のメリットは小さくなっていきます。
新築ではなく、建売住宅や中古住宅を購入する際には注意が必要です。
見た目は新しくても、省エネ基準を満たしていない物件が存在するため、購入前に必ず性能証明書の有無を確認しましょう。
資金計画を立てる際は、長い目で考えて余裕のある計画を立てましょう。
まずは無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスであなたが建てたい家の実際の資金計画を比較してみることをおすすめします。
具体的にかかる費用がわかれば、予算オーバーや家を建てた後の生計を圧迫するといったリスクを避けながら現実的な資金計画を立てることができますよ。
営業トークは一切ないので、ぜひご活用ください。
5.新築住宅の税金対策で知っておきたいこと
これから新築住宅を建てようと思っているけれど税金が心配な方や、税金を無駄に払いたくないと考える方はぜひ次の二つを意識してください。
それぞれ解説していきます。
5-1.税金の優遇制度をフル活用すること
新築時の税制優遇を受けるためには所定の手続きが必要な場合があります。
住宅ローン控除の手続きや、不動産取得税の軽減の申告などは忘れないようにしてください。
「認定長期優良住宅」や「ZEH住宅」のように性能の高い住宅は、税制優遇が大きくなります。
快適に過ごせる家を建てつつ、税金の優遇を最大限に活用したいときは積極的に検討しましょう。
高性能な住宅なら税制優遇だけでなく補助金制度も魅力!
高性能な住宅では様々な税金の優遇だけでなく、各種の補助金制度があります。
「ZEH補助金制度」では、ZEH(ゼッチ)を建てる場合には55万円、次世代ZEH(ZEH+)なら90万円の補助金を受けられます(2025年度)。(参考:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「 令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」)
令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」)
「子育てグリーン住宅支援事業」は、ZEHの新築で40万円、長期優良住宅の新築で80万円、GX志向型住宅は最大160万円の補助金が受け取れます。(参考:国土交通省「子育てグリーン住宅支援事業【公式】」)
新築住宅の補助金・減税制度の最新情報を確認しながら、お得な家づくりを検討しましょう。
また、解説してきた減税措置のほかにも、住宅を購入する際に使える税制優遇として節税効果が大きいのが以下の3つです。
「住宅取得資金の贈与の特例」は、親・祖父母からの住宅購入資金の贈与を一定額まで非課税で受け取ることができるという特例です(適用期間は2026年12月31日まで)。
非課税限度額は、一般の住宅であれば500万円、質の高い住宅であれば1,000万円となっています。
家を新築するタイミングは親世代から非課税で資産を移転する大きなチャンスです。なお、この制度を利用するには、確定申告をする必要があります。年齢、年収などの条件については国税庁ホームページでご確認ください。
参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 」
「認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除」が適用できることもあります。
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅のいずれかを取得した場合、45,300円×床面積(上限650万円)×10%が所得税額から控除されます。
2025年12月31日までの期限がありますが、合計所得金額が2,000万円以下の方なら利用できるため、該当するときは申請しましょう。
参考:国税庁「No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)」
「住宅を買い替えたときに譲渡益が生じた場合の課税繰り延べ」も、2025年12月31日までであれば適用されることがあります。
参考:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
適用できる控除制度・特例措置は、利用によりメリットが得られるか検討してみてください。
▶家づくりで補助金・減税制度を賢く活用する方法(無料)5-2.税金も考慮して資金計画をたてること
家を新築する際の資金計画を立てる際には、税金も念頭に入れておきましょう。
シミュレーション例では、土地・建物合わせて5,000万円の家の場合、最初に一度だけ負担する税金が約29万円、毎年かかる税金が約16万円でした(実際の税額は諸条件によって異なります)。
購入後は毎年の固定資産税の納税等も必要となるため、返済の計画にも余裕を持ちたいものです。
住宅ローン控除で戻ってくる分を、納税に充てる方法もあります。
しかし、住宅ローン控除は10年または13年で終わるため、還付される金額は「別物」と考えて、長期的に無理なく暮らせるように計画しましょう。
▶家づくりで補助金・減税制度を賢く活用する方法(無料)6.【2024年リフォーム減税】特例措置の拡充・延長
新築住宅で気になる点が見つかった際には、リフォームを検討できます。
もちろん、新築の段階で自分が思い描く理想通りに仕上げられればそれに越したことはありません。
しかし、どのようにこだわり抜いた住宅でも、必ず1つは後悔する点があるものです。
新築住宅での後悔例
- 間取りが思ったより使いにくかった
- 収納をもっと増やせばよかった
- 冷暖房効率が悪くなってしまった
新築住宅で気になる点をリフォームする際にも減税措置が適用される場合があるため、念のために押さえておきましょう。
まず、既存住宅において、耐震化・バリアフリー化・省エネ化・三世代同居化・長期優良住宅化のいずれかを実施する場合の措置です各工事にかかった金額のうち最大10%(上限は工事の内容に応じて60万~75万円)が所得税額から控除されます。(2025年12月31日まで)
また、上記の工事に加えて子育て関連のリフォーム工事に対しても、かかった金額の最大10%(上限25万円)が所得税額から控除されます。(2025年12月31日まで)
参考:国土交通省「 令和6年度 国土交通省税制改正概要」「
令和6年度 国土交通省税制改正概要」「 住宅のリフォームに係る税の特例措置」
住宅のリフォームに係る税の特例措置」
特例措置の期間は、延長されることも珍しくありません。
最新情報を集めながら、満足度の高い家に仕上げていきましょう。

柴田 充輝
税制優遇をフル活用するための手続きについては、タイミングが重要です。住宅ローン控除は入居年の翌年、不動産取得税の軽減申請は取得後60日以内(都道府県によって異なります)など、それぞれ期限が異なります。
ハウスメーカーや工務店との契約時に、必要な手続きスケジュールを確認し、カレンダーに記録しておくことをお勧めします。
補助金制度との併用については、予算枠の関係で早期に受付終了となる場合があります。ZEH補助金や子育てグリーン住宅支援事業は人気が高く、年度前半で締切となることも珍しくありません。
実質的に自己負担を軽減できるため、設計段階から補助金の申請スケジュールを考慮した計画を立てることが重要です。
住宅取得の資金計画については、住宅ローン控除終了後の家計負担増を織り込みましょう。
控除期間中の還付金は別途積み立て、将来のメンテナンス費用や税負担増に備えておけば、突発的な支出が発生してもあわてずに済みます。
まとめ
一戸建てを新築すると、「一度だけ払う税金」「毎年支払う税金」「戻ってくる税金」があります。
新築の時点で一度だけ発生する税金は、印紙税、登録免許税、不動産取得税です。
購入後に毎年納税するのは固定資産税、都市計画税です。
土地建物合わせて4,000万円で新築した場合のシミュレーションでは、購入時に約29万円の納税、購入後は毎年約16万円の納税、そして13年間毎年21万円の税金の還付が受けられるという結果になりました。
住宅ローン控除で戻ってくる税金は非常にお得です。また、制度の改正により環境に良い住宅であるほど減税制度などが手厚くなります。
家づくりプラン一括依頼で
複数ハウスメーカーを比較!
家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。
そこでおすすめなのがHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスです。
スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。
気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。
この記事の編集者