- 変更日:
- 2026.02.04
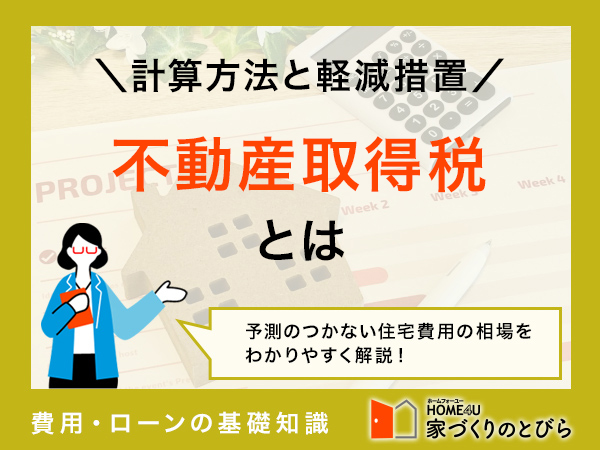
マイホームは人生最大の買い物です。
大きなお金を動かすからこそ、税金や諸費用についても事前に把握しておきたいですよね。
新築の注文住宅を建てるときに、意外と知られていないのが「不動産取得税」です。
不動産取得税は、不動産を取得した時に1度だけかかる税金です。
不動産取得税の税率は、土地・建物ともに3%(特例措置の適用後)です。新築住宅の不動産取得税の額は、固定資産税評価額×3%で計算できます。
ただし、新築住宅では軽減制度が使えることがほとんどで、不動産取得税がかからないケースもあります。
軽減措置を利用すればかなりの節税になるでしょう(詳細は2章で解説)。
この記事では以下の内容ついて解説していきます。
この記事でわかること
- 不動産取得税の仕組み
- 不動産取得税の計算方法と軽減措置
- 流れと申告方法、失敗しないポイント
不動産取得税を納税するタイミングは、注文住宅の完成から半年以上先になることがあります。
忘れたころに納税通知書が送られてくると焦ってしまうので、余裕をもって生計を立てるためにも、ぜひ参考にしてくださいね
無料

まとめて依頼

注文住宅にかかる費用内訳が知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
目次
1.不動産取得税の仕組み
はじめに、不動産取得税の課税対象や申告の仕組みを見ていきましょう。
1-1.不動産取得税が課税される対象は?
不動産取得税は、土地の購入や家屋の新築など、不動産を「取得」した際にかかる税金です。
具体的に言うと、次のようなときにかかります。
不動産取得税がかかるタイミング
- 家を建てるための土地を購入したとき
- 注文住宅を新築したとき
- 新築建売住宅や中古住宅を購入したとき
- 増築や改築を行ったとき
贈与や交換で取得する場合も含めて、不動産を取得した際はほとんどのケースで不動産取得税の課税対象となります。
ただし、相続で取得した場合は非課税です。
不動産取得税は取得した時に課せられる税金なので、毎年ではなく一度だけの課税です。
ちなみに、「固定資産税」と「都市計画税」は不動産を所有していると毎年課税されます。
なお、不動産取得税は都道府県税なので、不明点があるときの問い合わせは都道府県税事務所に行います。
1-2.不動産取得税の申告と支払い時期
不動産取得税の申告期限は、都道府県によって異なりますが、不動産を取得した日から10~60日以内に申告することとされています。
申告期限の一例
- 東京都:30日以内
- 神奈川県:10日以内
- 千葉県:60日以内
申告をしないと、各種の軽減措置が受けられないことがあるのでご注意ください。
ここでいう「不動産を取得した日」とは、土地や建物を購入したときは売買の決済を行った日(所有権の移転登記日)、注文住宅を新築したときは保存登記した日です。
なお、不動産の登記が動くと都道府県税事務所は把握できる仕組みになっているので、申告しなくても不動産取得税はかかります。
不動産取得税を申告すると、数ヶ月して納付書が送付されますが、納付期限は納付書が届いてから1~2ヶ月程度です。
実際に納税する時期は、家を建ててから1年近くになることもあるため、必要となる費用を忘れずに準備しておくと安心です。
家づくりを検討しだしたら、まずは無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスをご利用ください。
スマホやパソコンから簡単にあなたの予算に合ったハウスメーカー・工務店がわかるうえ、実際の住宅プラン(資金計画含む)を複数比較することができます。
ハウスメーカー・工務店があなたのために作成した住宅プランの費用がわかるので、無理のない資金計画を立てやすくなり、住み始めてからの家計にも配慮した家づくりが叶いますよ。
疑問点やお悩みが出た際には、コーディネーターや注文住宅のプロに無料で相談することもできます。
家づくりで予算オーバーしたり、家計を圧迫させたりしないために、ぜひご活用ください!
2.不動産取得税の計算方法と軽減措置
次に、不動産取得税の計算方法を詳しく解説します。
マイホームを購入したときは、ほとんどのケースで「軽減措置」の適用対象になるのでこちらも見ていきましょう。
2-1.不動産取得税の税率と計算式
不動産取得税は次のように計算できます。
固定資産税評価額×税率=不動産取得税額
不動産取得税の税率は原則4%です。
ただし、特例措置により、土地や住宅の税率は3%に軽減*されています。
また、宅地評価の土地は課税標準の特例措置により、評価額が2分の1*になります。
*土地: 2027年(令和9年)3月31日までに取得/住宅:2026年(令和8年)3月31日までに取得
参考:国土交通省「 令和6年度国土交通省税制改正概要」
令和6年度国土交通省税制改正概要」
不動産取得税の課税の基礎となる価格は、基本的には「固定資産税評価額」です(特殊な事情がある場合は都道府県知事が決定します)。
固定資産税評価額とは、各市町村の固定資産課税台帳に登録された価格で、売買価格や建築工事費用とは異なります。
固定資産評価の水準は、住宅なら建築費のおよそ50~60%程度、土地は時価の70%前後が一般的です。
固定資産課税台帳は所有者であれば各都道府県の役所等で閲覧することができますが、建物が新築の場合には新たに評価されるので事前に価格を確認できません。
▶理想の条件を押さえた家づくり、最適価格を知る方法(無料)2-2.不動産取得税がかからないケースとは
不動産取得税がかからないケースは以下の3つです。
- 「軽減措置」によって非課税になる
- 相続により不動産を取得した場合は非課税
- 不動産の価格が以下の「免税点」に満たない場合は非課税
| 区分 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 10万円 |
| 家屋を新築・増築・改築 | 23万円 |
| 家屋を売買・贈与などにより取得 | 12万円 |
2-3.軽減措置を使えば税金が安くなる
不動産取得税は、軽減措置を適用することで節税することができます。新築住宅とその敷地の軽減措置について詳しくみていきましょう。
建物部分の軽減措置
一定の条件を満たす新築住宅は、価格から1,200万円(一戸につき)が控除されます。
新築住宅の軽減措置を受けるには、建物の延べ床面積が50平米以上240平米以下で、居住するための建物であることが条件です。
軽減措置が適用されると、不動産取得税額の計算式は以下のようになります。
(建物の固定資産税評価額-1,200万円)× 3% =建物の不動産取得税額
最大で36万円(1,200万円×3%)が軽減されるため、大きな節税効果があります。
また、固定資産税評価額が1,200万円を超えない場合は建物の不動産取得税がかからないということになります。
住宅の固定資産税評価額は、建築費のおよそ50~60%くらいになるのが一般的なので、建物の不動産取得税が非課税になるケースは珍しくありません。
また新築の場合、認定長期優良住宅なら1,300万円の控除を受けることができます。
土地の軽減措置
上記の「新築住宅の軽減措置」が適用されるケースでは、その敷地についても不動産取得税の軽減があります。
軽減措置が利用できる場合、土地の不動産取得税額の計算式は以下の通りです。
((土地の固定資産税評価額 × 1/2)× 3%)– 軽減額 =土地の不動産取得税額
軽減額は下記の2つのうち、金額の大きい方となります。
- 45,000円(税額45,000円未満はその金額)
- 土地1平米あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平米まで)×3%
土地の軽減措置を受けられるのは、土地を購入して3年以内に注文住宅を建てた人や、新築の土地付建売住宅を購入した場合などです。詳しい要件は各都道府県税事務所のホームページなどでご確認ください。
参考:東京都 新築住宅用の土地の軽減要件
【土地を先に取得した場合】
土地を取得後3年以内に、当該土地上に住宅が新築されていること。
ただし、次の1・2のいずれかに該当する場合に限る。
- 土地の取得者が、住宅の新築までその土地を引き続き所有していること
- 土地の取得者からその土地を取得した方(譲渡の相手方)が、住宅を新築したこと
【新築住宅を先に取得した場合(同時取得を含む)】
- 住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること
- 新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む)に同じ方が取得していること
参考・引用:東京都主税局「都税:不動産取得税 | 都税Q&A 」
「希望するエリアの土地相場はいくらぐらい?」「そもそも、自分が建てたい家はどれぐらいの建築費がかかる?」といった疑問をお持ちの方には、無料の「HOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービス」がおすすめです。
どう進めていいかわからない方へ
ハウスメーカーと土地は
同時に探すのがおすすめ!
土地費用を抑え、家にお金をかけられた
ノウハウ豊富なハウスメーカーに相談できたから、斜面など、特殊なぶん安価な土地でも希望通りの家が建てられた!
諦めない方法
HOME4U「家づくりのとびら」経由で
注文住宅を契約・着工の方全員に
Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!
3.不動産取得税の計算シミュレーション
不動産取得税について、以下の条件で実際の計算をシミュレーションしてみましょう。
例
2021年4月に160平米の土地を取得して、同年10月に床面積120平米の住宅を新築し、固定資産税評価額が家屋:1,500万円、土地:1,200万円の場合を例に計算していきます。
なお、2,500万円の工事代金で注文住宅を建てた場合、工事請負金額の2,500万円がそのまま固定資産税評価額になるわけではありません。
固定資産税評価額は建築費の5~6割ほどになるのが一般的なので、ここでは固定資産税評価額は1,500万円として計算してみます。
3-1.建物の不動産取得税
軽減措置を受けないときは、「不動産取得税額=固定資産税評価額×税率」で、居住目的の場合の税率は3%でしたので、1,500万円×3%=45万円です。
しかし、新築住宅の軽減措置を受けると、(1,500万円–1,200万円)×3%=9万円となります。
認定長期優良住宅なら、1,300万円の控除を受けられるので、(1,500万円–1,300万円)×3%=6万円となります。
▶家づくりで補助金・減税制度を賢く活用する方法(無料)3-2.土地の不動産取得税
例えば1,700万円で土地を購入した場合でも、売買価格の1,700万円に税率をかけるのではありません。
固定資産税評価額は時価の7割程度が多いので、ここでは固定資産税評価額1,200万円という前提で計算してみます。
軽減措置を受けないと、「不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×税率」ですから、1,200万円×1/2×3%=18万円となります。
土地の軽減措置を受けると、
「不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×税率-軽減額」
=1,200万円×1/2×3%-軽減額となります。
軽減額を最後に引く点が土地の不動産取得税を算出する際のポイントです。
【軽減額(225,000円)の算出方法について】
軽減額の計算は、下記のうち大きい金額になります。
(a)45,000円(税額45,000円未満はその金額)
(b)土地1平米あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平米まで)×3%
(b)を計算してみると、
固定資産税評価額(1,200万円×1/2)÷土地面積160平米×200(住宅の床面積120平米×2=240平米になるため200として計算)×3%=225,000円
となります。
土地の軽減額は、この計算によって出された金額か45,000円のどちらか大きい方を適用することができるので、今回は225,000円の方を適用します。
つまり、1,200万円×1/2×3%-225,000 < 0円 なので、土地の不動産取得税は0円(非課税)となります。
家づくりの際には、まず無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスであなたが建てたい家の実際の資金計画を比較してみましょう。
具体的にかかる費用がわかれば、予算オーバーや家を建てた後の生計を圧迫するといったリスクを避けながら現実的な資金計画を立てることができますよ。
営業トークは一切ないので、ぜひご活用ください。
4.【所有する土地に新築する場合】不動産取得税を支払う流れと申告方法
ここからは、不動産取得税の申請の方法や支払方法についての流れを詳しくみていきましょう。
4-1.自分の土地に新築したなら建物だけ課税対象
建て替えの場合には、建物だけに不動産取得税が発生します。
もともと所有していた自分の土地に注文住宅を新築する場合も、建物だけが課税対象です。
土地は新たに「取得」したわけではないので、不動産取得税がかかりません。
4-2.建物の不動産取得税の申告方法
申告方法については、住宅を新築した後に「不動産取得税申告書」や「不動産の取得申告書」を管轄の都道府県税事務所に提出します(書式は都道府県ごとに異なります)。
多くの自治体では、「不動産取得税申告書」は税事務所窓口で受け取るか、ホームページでダウンロードすることが可能です。
申告書の提出期限は都道府県によって異なり、不動産の「取得日」から10~60日程度となっています。「取得日」とは、建物の竣工日や入居を始めた日などではなく、建物の登記をした日です。
軽減制度の適用を受ける場合は、軽減の適用を受ける旨も併せて申告します。
申告書の提出後は、都道府県事務所から不動産取得税の納付書が届き、納税します。
なお、軽減措置によって納税額が0円となった場合には納付書は届きません。
新築の場合に納付書が届く時期は、建物の登記から半年~1年以上かかることもあります。
納付書が届いたら、納税は期限内に済ませましょう。
都道府県税事務所窓口や金融機関、コンビニエンスストア、ペイジー、クレジットカード等で支払うことができます。もし遅延してしまった場合、延滞金が発生する可能性があるのでご注意ください。
【不動産取得税を申告しないとどうなる?】
新築後に不動産取得税の申告を忘れてしまっても、不動産取得税の課税対象ならば納付書は届きます。
建物の登記が動けば、都道府県税事務所は把握できる仕組みになっているからです。
実は、不動産取得税を知らず、申告を忘れてしまって納付書が届いてから手続きする人は珍しくないのです。
納付書が届いたときに、納付期限までに納税すれば延滞税などはかかりません。
しかし、申告をしなかった場合には、新築住宅の軽減措置が適用されていない可能性があります。
一方で、申告をしなくても、新築住宅の軽減の要件に当てはまることが県税事務所によって確認できたケースでは自動的に軽減措置を適用してくれることもあります。
また、長期優良住宅で1,300万円の控除を受けたいときは必要書類の提出が必要となるため、県税事務所等から納付書が届くときに「長期優良住宅の方はこのような書類を提出してください」という案内が同封されているはずです。
「納付書が来たけれど申告・申請が必要かどうかよくわからない」という場合は、お住まいの地域の都道府県税事務所に問い合わせてみると安心です。
「家づくりは建てる前も後も流れが難しい」と感じるかもしれませんが、大手のような優良ハウスメーカー・工務店であれば、家づくりのステップやポイントをしっかり伝えてくれるので安心してくださいね。
信頼できるハウスメーカー・工務店の中から、あなたに合ったハウスメーカー・工務店を探す際には、ぜひ無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスをご利用ください。
全国に数万社あるといわれている大手ハウスメーカー・工務店の中から、スマホ・パソコンで簡単にあなたの要望や予算に合ったものをピックアップできるうえ、最大5社分まで実際の住宅プラン(資金計画含む)を比較できます。
あなたにとってベストなハウスメーカー・工務店を効率よく見つけるために、ぜひご活用ください。
5.【土地を買って新築する場合】不動産取得税を支払う流れと申告方法
土地を買ってから注文住宅を新築する場合は、まず先に買った土地の分の不動産取得税を申告し、建物を建てたあとにも申告をします。
5-1.まずは土地を購入した分の不動産取得税を申告する
土地を購入したら、管轄している都道府県税事務所に不動産取得税の申告を行うのが原則です。
申告期限は取得日から10~60日程度(都道府県によって異なる)。
取得日は土地の所有権移転登記を行った日(決済日)を指します。
住宅の敷地の軽減制度に該当するときは、不動産取得税申告書に建築予定の建物についても記載しておきます。
「この土地に3年以内に家を建てるので、税金を軽減してください」という届出をし、添付書類として、建築確認済証や工事請負契約書のコピーも添付。
そして、住宅が完成したら登記事項証明書などを提出します。
提出書類は都道府県によって異なるので、各自治体の県税事務所等で確認してください。
その後、都道府県税事務所から不動産取得税の納付書が届いたら納税を行います。
5-2.猶予申請を行えば納税を待ってもらえる
土地の不動産取得税を納付するタイミングについては猶予申請と還付申請の2つの方法があり、基本的には猶予申請をするのがおすすめです。
猶予申請とは、新築住宅が完成するまでの間、土地にかかる不動産取得税の全部または一部の納税を猶予してもらえる制度です。
つまり、住宅が完成すれば土地の税金が減額される見込みの場合に、土地の不動産取得税の支払いを待ってもらえるということです。猶予申請は、納付期限までに手続きが必要なので早めに申請してください。
猶予申請を行うには、「軽減措置の対象となる条件を満たしている建物が、その土地の上に3年以内に新築されることが確実である」などの条件が必要となります。
条件を満たしている場合、「建築確認済証」や「確認申請書」の一部を都道府県税事務所に提出して申請することで、軽減される税額分を猶予してもらうことができます。
5-3.還付申請もできる
一方、還付申請は、納税通知書通りの不動産取得税をいったん納付し、建物が完成した後で軽減税率を申告して払い過ぎた分の税額を還付してもらう(返金してもらう)方法です。
最初に送られてくる土地の不動産取得税は、軽減措置を受けていないので高額になる可能性もあり、納税資金をいったん準備しなければならないのがデメリットといえます。
還付申請を行う場合、都道府県税事務所から納税通知書が届いたら、額面通りの不動産取得税を納税します。
その後、家が完成してから、「不動産取得税減額申請書」「登記事項証明書」などの必要書類を提出して手続きをすることで還付を受けられます。
還付には5年程度の期限があるので注意してください。
【不動産取得税の申告をしないとどうなる?】
不動産の登記があると県税事務所等にはわかるようになっているため、申告しなくても不動産取得税は課税されます。
不動産の取得を申告していない場合、軽減措置が適用されていない可能性が高いです。
ただし申告せずに納付書が送られてきた場合でも、納付期限までなら減額措置や納税猶予の手続きができる場合があります。
申告しないうちに納付書が送られてきて、別途手続きが必要かどうかわからないときは都道府県税事務所に問い合わせてみましょう。
6.不動産取得税で失敗しないためのポイント
注文住宅を建てようとしている場合に覚えておきたいポイントを最後にご紹介します。
6-1.土地を購入したら3年以内に建てないと損
土地を購入して注文住宅を建てようと考えている方にご注意いただきたいのは、土地を購入してから3年以内に新築しないと損になるという点です。
3年以内に新築しないと、不動産取得税について住宅用地の軽減を受けられなくなります。
「3年以内に新築」という条件は、建物の完成後に登記をするまでなので、そこから逆算して建物プランを練る必要があります。
本記事でご紹介したシミュレーション では、時価1,700万円(固定資産税評価額1,200万円)の土地で軽減措置を受けないと、不動産取得税額は18万円でした。
新築のタイミングが遅かっただけで住宅用地の軽減を受けられないのは非常にもったいないですよね。
また、軽減税率の3%が適用されるのは2024年2月現在、以下のとおりです。
軽減税率3%の適用期限
- 土地: 2027年(令和9年)3月31日までに取得
- 住宅:2026年(令和8年)3月31日までに取得
参考:国土交通省「 令和6年度国土交通省税制改正概要」
令和6年度国土交通省税制改正概要」
住宅ローン控除などの他の補助金や税金の税制優遇も現在は拡充されていることや、住宅ローンが超低金利水準であることを考えても、建築プランを早めに検討して家を完成させることをおすすめします。
6-2.しっかりと資金計画を立てよう
注文住宅を建てるときには建物の工事費用以外に税金や諸費用がかかります。
これらはローンで支払うのではなく、通常はすぐに支払う必要があるため手元に費用を準備しておきたいものです。
不動産取得税については新居に引っ越した後に納付するので、後で慌てないためにも予想される税額を計算しておくと安心です。
無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスを活用しながら、あなたの建てたい家の費用相場を把握し、現実的な資金計画を立ててくださいね。
まとめ
それではおさらいです。
本記事では不動産取得税について詳しく解説してきました。
新築住宅・注文住宅については、評価額から1,200万円(長期優良住宅なら1,300万円)を控除できる制度があり、税率は3%です※。一定の要件を満たせば土地についても減額制度があります。
※土地:2027年3月31日まで/住宅:2026年3月31日まで
土地を買って注文住宅を新築する場合や、新築建売住宅を購入すると、土地と建物の両方に不動産取得税がかかります。
一方、建て替えの場合は土地を新たに取得するわけではないため、建物だけに不動産取得税がかかります。
不動産取得税は1度だけの税金とはいえ、忘れたころに課税されると負担に感じるので、適用される軽減措置を見落とさないようにして税額の負担を減らしましょう。
注文住宅にかかる費用内訳特集
家づくりプラン一括依頼で
複数ハウスメーカーを比較!
家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。
そこでおすすめなのがHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスです。
スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。
気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。
この記事の編集者
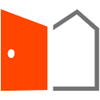
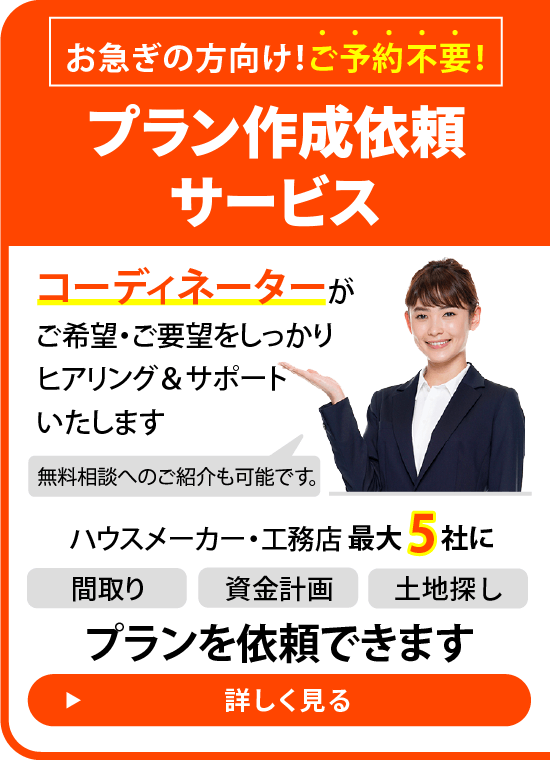
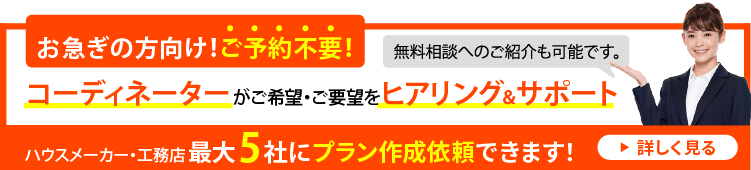
まさかの…土地探しが振り出しに!?
住みたいエリアの条件だけで土地を探していたけど、よくよく建てる家を考えた結果、4人家族の家にするには狭すぎて断念…。