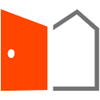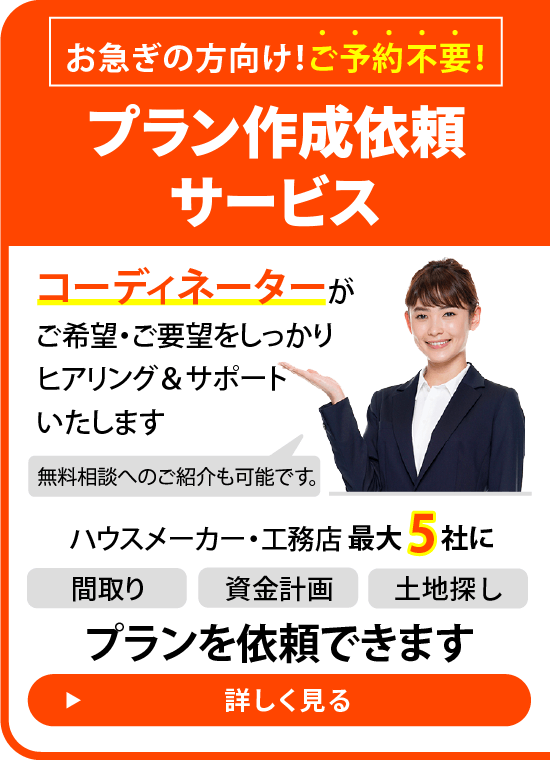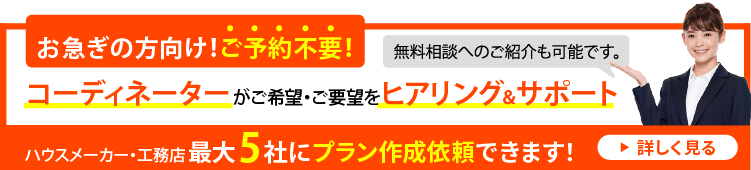- 変更日:
- 2026.02.03
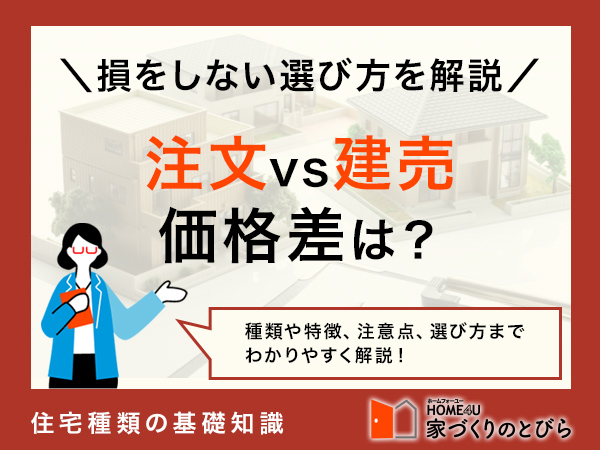
注文住宅(フルオーダーの一戸建て)と建売住宅(分譲住宅)は、どちらも新築の一戸建てを手に入れる方法ですが、価格差は非常に大きな検討材料になります。以下では住宅金融支援機構や国土交通省の統計をもとに、直近の価格差や地域差、価格差が生じる理由、選び方のポイントを詳しく解説します。
この記事でわかること
- 注文住宅と建売の違い
- 注文住宅と建売の価格差
- 注文住宅と建売のメリット、デメリット
無料
まとめて依頼
家づくりを検討し始めたら「HOME4U(ホームフォーユー)家づくりのとびら 」で情報収集を始めましょう。
- 建売住宅
不動産会社やハウスメーカーが土地を区画し、同じ仕様の住宅を複数棟建てて土地とセットで販売するもの。完成済み、または完成予定の住宅を購入する形態で、価格・間取り・設備などがあらかじめ決まっています。完成物件を実際に確認できるためイメージが掴みやすく、購入後すぐに入居できるのが特徴です。
- 注文住宅
施主が土地を購入した上で建築士やハウスメーカーに設計を依頼し、希望に沿って自由に間取りや設備を決めて建てる住宅です。自由度が高い反面、土地探しや打ち合わせに時間と手間がかかり、建築費用も変動しやすいのが特徴です。
目次
2. 最新データによる価格差の推移
住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」は毎年、建売住宅と土地付き注文住宅の取得費用を公表しています。調査方法や年度によって集計条件が異なるため、価格差は年によって変動します。
| 年度 | 公的機関発表のデータ | 出典 |
|---|---|---|
| 2024年度 (令和6年度) | 所要資金の全国平均は、 ・土地付注文住宅5,007万円 ・建売住宅3,826万円 土地付注文住宅と建売住宅の差額は約1,181万円です。 | 住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査結果」 |
| 2023年度 (令和5年度) | 所要資金の全国平均は、 ・土地付注文住宅4,903万円 ・建売住宅3,603万円 土地付注文住宅と建売住宅の差額は約1,300万円です。 | 国土交通省「関連データ等について」(住宅価格の推移/所要資金の推移) |
| 2022年度 (令和4年度) | 所要資金の全国平均は ・土地付注文住宅4,694万円 ・建売住宅3,719万円 土地付注文住宅と建売住宅の差額は約975万円です。 | 住宅金融支援機構「2022年度フラット35利用者調査結果」 |
これらの公的データに基づけば、建売住宅と土地付注文住宅の価格差は2022年度で約975万円、2023年度で約1,300万円、2024年度で約1,181万円と年次によって変動していることがわかります。
特に2023年度については国土交通省の資料で住宅価格が全般的に上昇傾向にあることが指摘されており、土地付注文住宅の価格が2013年度の3,637万円から2023年度には4,903万円へ約1.35倍上昇したのに対し、建売住宅は3,320万円から3,603万円へ約1.09倍の上昇に留まっています。
3. 価格差が生まれる主な要因
価格差は単に「注文住宅が贅沢だから高い」というだけでなく、構造的な要因が複数絡んでいます。
3‑1. 敷地面積・延床面積の違い
令和4年度フラット35調査では、建売住宅の平均延床面積は101.6㎡、土地付き注文住宅は111.2㎡、注文住宅(建て替えを含む)は119.5㎡でした。平均で約8~18㎡(2~5坪)広いため、その分の建築費と土地費用が上乗せされます。敷地面積についても前述のように平均で約68㎡の差があり、土地取得費用の差につながっています。
3‑2. 設計費用・打合せコスト
注文住宅は建築士や設計士によるオーダーメイド設計が必要で、そのコンサルティング費用が加算されます。また、施主の希望に応じて設備や素材を自由に選べるため、こだわりが強いほど費用が高くなりがちです。特殊な間取りや地下室・屋上などを採用すると地盤改良や特殊工法が必要になることもあり、建設費が増える傾向にあります。
3‑3. 材料仕入れと工期の違い
建売住宅は同じ仕様の住宅を複数棟建てるため、建材や設備を大量に一括仕入れすることで単価を抑えられます。工事も効率化されており、同じ間取り・仕様であれば職人の配置や工期を短縮できるため人件費が削減される傾向にあるでしょう。
- 土地を一括で仕入れる
- 設計を限定する
- 工期を短縮する
- 資材を大量に仕入れる
などが建売住宅のコストダウンの理由として挙げられています。
3‑4. 製品の仕様・性能の違い
注文住宅は耐震性能や断熱性能、外壁材やフローリング材などを施主が選べるため、性能にこだわるほど費用が上がります。一方、建売住宅は標準仕様が決まっているため性能のばらつきは小さく、設計変更やオプションの手間が不要です。ただし、建売住宅でも長期優良住宅認定や高断熱仕様の物件も増えているため、性能を確認したうえで選ぶことが重要です。
「注文住宅」や「建売住宅」で迷っていて、「なかなかアクションを起こせない」とお悩みであれば、まずは無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスであなたに合ったハウスメーカー・工務店を調べて、その中から複数社の実際の住宅プランを見比べてみてください。
実際の住宅プランを見てからモデルハウスに見学に行くと、そのハウスメーカー・工務店への理解がより一層深まり、建築依頼先の検討がスムーズになります。
4. 価格差以外の比較ポイント
価格だけでなく、ライフスタイルや価値観によって最適な住宅形態は異なります。以下では価格差以外の主な比較ポイントを紹介します。
4‑1. 入居までの期間
建売住宅はすでに完成または建築中の物件を購入するため、契約から入居までの期間が短く済みます。建売住宅の入居までの期間は土地購入から約数か月であるのに対し、土地取得と設計・建築を経る注文住宅は半年以上~1年程度かかるとも言われています。転勤や子どもの入学など入居時期が決まっている場合は建売住宅も視野にいれるのもおすすめです。
4‑2. 自由度と満足度
注文住宅の最大の魅力は、間取りや設備を自由に設計できることです。一方、建売住宅は自由度が限られるものの、最近は消費者のニーズを反映して人気の間取りや設備が標準仕様に含まれていることも多く、コストを抑えつつ満足度の高い物件が増えています。
4‑3. 資金計画と契約の手間
建売住宅では土地と建物を一括で購入するため資金計画が立てやすく、契約も1度で済みます。注文住宅の場合は土地の売買契約と工事請負契約を別々に締結し、工事の進捗に合わせて支払いが発生するため資金計画が複雑になりがちです。
4‑4. 住宅性能と寿命
住宅の寿命は工法やメンテナンスに左右され、注文住宅と建売住宅で大きな差はありません。長期優良住宅認定や住宅性能表示制度など、法令に基づいた性能を満たしているかを確認することが大切です。建売住宅でも耐震等級3やZEH仕様など高性能な物件が増えています。
5. 価格差を踏まえた選び方のポイント
- 予算と資金計画を明確にする
土地購入を含めた総予算や自己資金、ローンの借入可能額を把握しておくことが第一歩です。建売住宅は総費用を把握しやすく、注文住宅は設備グレードや設計変更で費用が増える可能性を考慮します。
- 地域の相場を確認する
土地価格が高い都市圏では価格差が大きくなる傾向があるため、希望する地域の土地相場や建築費を調べたうえで検討しましょう。特に東海や南関東など土地価格が高い地域では注文住宅の総費用が大きくなりやすいです。
- ライフスタイルや価値観を重視する
家づくりにこだわりたい、建築過程を楽しみたい人は時間と費用がかかっても注文住宅が向いています。一方、入居時期が迫っている、間取りに大きなこだわりがない人は建売住宅が適しています。
- 性能と保証を確認する
価格差だけでなく、住宅性能や保証内容も比較することが重要です。同じ価格帯でも耐震等級・断熱性能・長期保証などでコストパフォーマンスが変わります。建売住宅でも性能表示が明確な物件を選べば安心です。
- セミオーダー住宅という選択肢
注文住宅より自由度は低いものの、間取りや内装をある程度選べるセミオーダー住宅(建築条件付き土地など)は、価格を抑えつつ希望を反映できる中間的な選択肢です。住宅金融支援機構の調査では、建築条件付き土地を購入した世帯と完全注文住宅の世帯を合計すると新築購入者全体の44%を占めており、多くの人が自由度と価格のバランスを求めていることが分かります。
建売住宅にしようか注文住宅にしようか迷うという方は、一度注文住宅の住宅プランを見てみて、具現化された自身の要望を確認してもよいでしょう。
無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスなら、簡単にハウスメーカー・工務店があなたのために作成した住宅プランを複数比較できるので、あなたが建てようとしている家の具体的なプランや、費用相場、各社の提案内容の違いがイメージしやすいです。
効率的にマイホームを手に入れるために、ぜひご利用ください。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 注文住宅と建売住宅の価格差はどのくらいですか?
住宅金融支援機構のデータでは、年度や集計方法によって差が異なります。2024年度フラット35利用者調査では全国平均で約1,181万円、2023年度調査(総費用)では約1,300万円、2022年度調査では約975万円の差となっています。
Q2. 価格差は地域によってどのくらい違いますか?
2024年度の所要資金の平均値と、その差額(注文住宅-建売住宅)を示しています。数字はいずれも万円単位です。所要資金の内訳は、土地付注文住宅が「建設費+土地取得費」、建売住宅が「建設費+土地取得費+その他費用」です。
| 地域 | 土地付注文住宅の所要資金 (建設費+土地取得費) | 建売住宅の所要資金 (建設費+土地取得費+その他費用) | 差額 (注文住宅-建売住宅) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 建設費3,512.0万円+土地取得費1,495.1万円=5,007.1万円 | 建設費3,260.4万円+土地取得費322.8万円+その他費用242.9万円=3,826.1万円 | 約1,181万円 | JHF「2024年度フラット35利用者調査・集計表」 |
| 首都圏 | 建設費3,505.6万円+土地取得費2,285.0万円=5,790.6万円 | 建設費3,638.3万円+土地取得費411.0万円+その他費用313.8万円=4,363.1万円 | 約1,428万円 | |
| 近畿圏 | 建設費3,366.7万円+土地取得費1,826.0万円=5,192.7万円 | 建設費3,290.8万円+土地取得費282.3万円+その他費用253.4万円=3,826.5万円 | 約1,366万円 | |
| 東海圏 | 建設費3,615.7万円+土地取得費1,359.8万円=4,975.5万円 | 建設費2,896.3万円+土地取得費189.9万円+その他費用163.1万円=3,249.3万円 | 約1,726万円 | |
| その他地域 | 建設費3,549.1万円+土地取得費985.0万円=4,534.1万円 | 建設費2,709.8万円+土地取得費242.5万円+その他費用142.6万円=3,094.9万円 | 約1,439万円 |
フラット35利用者調査の集計表に基づけば、地域別の価格差は東海圏で特に大きく、その他の地域でも1,300〜1,400万円台と大きな開きがあることが分かります。土地付注文住宅は敷地面積・建設費が大きく、土地取得費も高額になりやすいため、建売住宅と比べて総所要資金が高くなるのが主な理由です。
Q3. 価格差以外に注意すべきポイントは?
自由度や入居までの期間、資金計画の複雑さ、住宅性能などが重要です。注文住宅は間取りや設備を自由に選べる反面、土地探しや設計の打合せに時間と手間がかかり、予算オーバーのリスクもあります。建売住宅は購入後すぐに入居でき、費用も明確ですが、間取りや仕様の変更は基本的にできません。また、建売住宅でも耐震性能や断熱性能が高い物件を選ぶことで、長く安心して暮らせるでしょう。
まとめ
注文住宅と建売住宅の価格差は、年度や地域によって数百万円〜1,500万円程度まで幅があります。これは敷地面積や延床面積の違い、設計費用、材料の仕入れ方、工期の効率化など複数の要因が影響しているためです。価格差だけに囚われず、ライフスタイルや希望する性能、入居時期を踏まえて選択することが大切です。公的な統計を確認し、資金計画や相場を把握した上で、自分にとって最適な家づくりを実現しましょう。
家づくりプラン一括依頼で
複数ハウスメーカーを比較!
家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。
そこでおすすめなのがHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスです。
スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。
気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。
この記事の編集者