- 変更日:
- 2026.02.04

本記事を読めば、1,000万円の住宅ローンを組んだ時の「金銭面でのインパクト≒生活に与える影響」についてイメージが具体的につくようになります。
この記事でわかること
- 住宅ローン1,000万円の毎月の返済額・総支払額・無理なく返済できる年収
- 住宅ローン1,000万円を組むために最低限必要な年収
- 1,000万円で家を建てる際のおすすめハウスメーカー 等
無料

まとめて依頼

何歳までに住宅ローンを組めばよいかお悩みの方はこちらの記事もご覧ください。
目次
1.【まとめ】住宅ローン「1,000万円」の毎月返済額・総支払額・年収目安
返済期間別に、住宅ローンを1,000万円借りた際の「毎月の返済額」「総支払額」「無理なく返済できる年収の目安」を表にまとめてみました。
| 返済期間 | 毎月の返済額 | 総支払額 | 無理なく返済できる年収目安 |
|---|---|---|---|
| 15年 | 約6万円 | 約1,120万円 | 年収300万円程 |
| 25年 | 約4万円 | 約1,200万円 | 年収200万円程 |
| 35年 | 約3万円 | 約1,300万円 | 年収160万円程 |
※頭金なし、ボーナス払いなし
※金利は全期間固定金利1.5%で計算
次章では、金利・返済期間別に、さらに詳細に「毎月の返済額」「総支払額」を見ていきます。
▶理想の条件を押さえた家づくり、最適価格を知る方法(無料)2.【早見表】住宅ローン「1,000万円」の毎月の返済額・総支払額
返済期間と金利によって、毎月の返済額は変わります。
住宅ローン1,000万円を借りた時の「毎月の返済額」と「総支払額」を、返済期間・金利から算出して以下の表にまとめました。
| 金利(%) | 返済額 | 返済期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||
| 0.5 | 毎月返済額 | 5.8 万円 | 4.4 万円 | 3.5 万円 | 3.0 万円 | 2.6 万円 |
| 総支払額 | 1,038 万円 | 1,051 万円 | 1,063 万円 | 1,077 万円 | 1,090 万円 | |
| 1.0 | 毎月返済額 | 6.0 万円 | 4.6 万円 | 3.8 万円 | 3.2 万円 | 2.8 万円 |
| 総支払額 | 1,077 万円 | 1,103 万円 | 1,130 万円 | 1,157 万円 | 1,185 万円 | |
| 2.0 | 毎月返済額 | 6.4 万円 | 5.6 万円 | 4.2 万円 | 3.7 万円 | 3.3 万円 |
| 総支払額 | 1,158 万円 | 1,214 万円 | 1,271 万円 | 1,330 万円 | 1,391 万円 | |
| 3.0 | 毎月返済額 | 6.9 万円 | 5.5 万円 | 4.7 万円 | 4.2 万円 | 3.8 万円 |
| 総支払額 | 1,243 万円 | 1,331 万円 | 1,422 万円 | 1,517 万円 | 1,616 万円 | |
※元利均等返済、ボーナス時の返済なしで試算
※住宅ローンシミュレーションを利用
※毎月返済額は1,000円以下四捨五入、総支払額は1万円未満切り捨て
毎月の返済額は、金利が低ければ低いほど、返済期間が長くなればなるほど、少なくなります。
一方で、返済期間が長くなればなるほど、総支払額は増えることに注意しましょう。
住宅ローンの金利相場について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
年収がいくらであっても、まずはHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービス(無料)で、あなたが建てたい家の費用相場を確認し、現実的な予算を把握しておきましょう。
あなたの予算に合ったハウスメーカー・工務店をピックアップできるうえ、実際の費用や住宅プランを確認しながら検討できるので、難しい資金計画がスムーズに立てられますよ。
3.【早見表】「住宅ローンの借入額別」無理なく返済できる年収
ここでは、住宅ローンの借入額によって、どのくらいの年収が必要なのか比較できるように、「無理なく返済できる年収」を返済期間と金利から算出して以下の表にまとめました。
| 住宅ローン 借入額 | 金利(%) | 返済期間/ 無理なく返済できる年収 | ||
|---|---|---|---|---|
| 15年 | 25年 | 35年 | ||
| 1,000万円 | 0.5 | 276万円 | 170万円 | 124万円 |
| 1.5 | 298万円 | 192万円 | 147万円 | |
| 2.5 | 320万円 | 215万円 | 172万円 | |
| 2,000万円 | 0.5 | 554万円 | 340万円 | 249万円 |
| 1.5 | 596万円 | 384万円 | 294万円 | |
| 2.5 | 640万円 | 430万円 | 343万円 | |
| 3,000万円 | 0.5 | 830万円 | 510万円 | 374万円 |
| 1.5 | 894万円 | 576万円 | 441万円 | |
| 2.5 | 960万円 | 645万円 | 515万円 | |
| 4,000万円 | 0.5 | 1,107万円 | 680万円 | 498万円 |
| 1.5 | 1,192万円 | 768万円 | 696万円 | |
| 2.5 | 1,280万円 | 860万円 | 687万円 | |
| 5,000万円 | 0.5 | 1,384万円 | 850万円 | 623万円 |
| 1.5 | 1,490万円 | 960万円 | 735万円 | |
| 2.5 | 1,600万円 | 1,075万円 | 859万円 | |
※元利均等返済、ボーナス時の返済なしで試算
※1万円未満四捨五入
金利や返済期間によっては、家の予算を上げることが可能かもしれません。
借入額別で「ローンを組んだ時のイメージ」を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事
4.住宅ローン「1,000万円」を組むために最低限必要な年収
ずばり
1,000万円の住宅ローンを組むために最低限必要な年収は、年収130万円です。
※返済期間35年、全期間固定金利1.5%の場合
例えば、住宅金融支援機構の【フラット35】では、「年収400万円未満では返済負担率を30%以内(400万円以上では35%以内)に収める」ことがローンを組む条件の一つです。
返済負担率とは、年収のうち年間返済額がどれだけの割合を占めているかを示す数値のことで、以下の式で求められます。
返済負担率 計算式
返済負担率(%)=年間返済額/額面年収×100
年収130万円あれば返済負担率を30%以内に収められるので、少なくとも【フラット35】でローンを組むことが可能です。
ただし、一般的に住宅ローンを無理なく返済するには、返済負担率を「25%以内」に収めるべきと言われています。
限度額ギリギリまで借りるのではなく、自分の生活を圧迫しない返済計画を立てましょう。
5.「1,000万円」で家を建てるならローコストハウスメーカーがおすすめ
ハウスメーカーの中には、広告費を削減したり、仕入れ方法を工夫したりすることで、他のハウスメーカーよりもコストを抑えて家を建てられるハウスメーカーがあります。
ローコストで家を建てられるおすすめハウスメーカー 一覧
- アイダ設計
- アイフルホーム
- アエラホーム
- ユニバーサルホーム
- ヤマダホームズ
- 桧家住宅
- タマホーム
- レオハウス
- 富士住建
おすすめのローコストハウスメーカーについて詳しく知りたい方や、1,000万円で建てられる家のイメージを持ちたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
「住宅ローンに関する記事」を他にも用意しております。あわせてご覧ください。
関連記事
この記事のポイント まとめ
住宅ローン「1,000万円」の毎月返済額・総支払額・年収目安
住宅ローン1,000万円の毎月の返済額・総支払額は以下のとおりです。
| 返済期間 | 毎月の 返済額 | 総支払額 | 無理なく返済できる年収目安 |
|---|---|---|---|
| 15年 | 約6万円 | 約1,120万円 | 年収300万円程 |
| 25年 | 約4万円 | 約1,200万円 | 年収200万円程 |
| 35年 | 約3万円 | 約1,300万円 | 年収160万円程 |
詳しくは「1.まとめ住宅ローン「1,000万円」の毎月返済額・総支払額・年収目安」で解説しています。
住宅ローン「1,000万円」を組むために最低限必要な年収
1,000万円の住宅ローンを組むために最低限必要な年収は「130万円」です。
ただし、限度額ギリギリまで借りると生活を圧迫する可能性があるので、無理のない返済計画を立てましょう。
詳しくは「4.住宅ローン「1,000万円」を組むために最低限必要な年収」で解説しています。
住宅ローン特集
家づくりプラン一括依頼で
複数ハウスメーカーを比較!
家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。
そこでおすすめなのがHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスです。
スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。
気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。
この記事の編集者
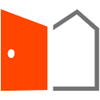
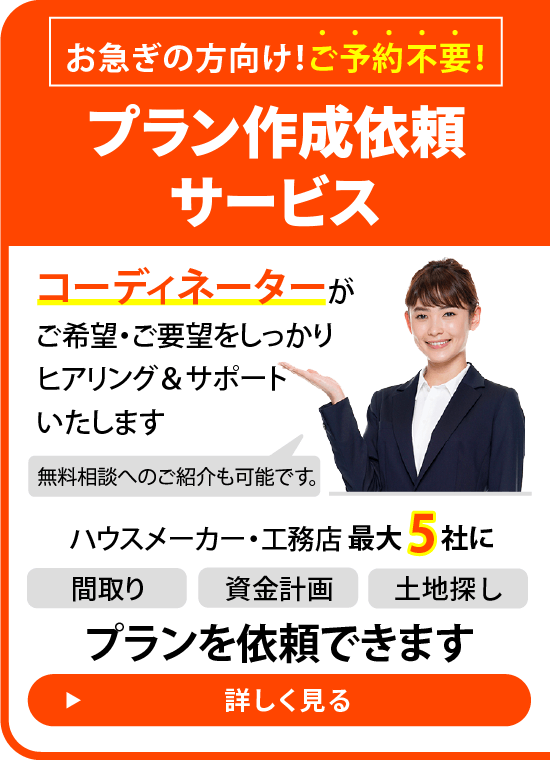
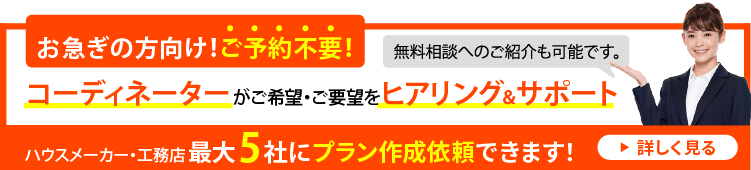
無料サポートサービスのご紹介
あなたの家づくりの検討状況や検討の進め方にあわせて、ご活用ください!
実際の建築プランを複数みて、
比較・検討したい
複数のハウスメーカーの建築プランが、かんたんな入力だけで、無料でもらえる「プラン作成サービス」がおすすめ!
費用や、ハウスメーカー選びの
コツを詳しく直接聞きたい
ハウスメーカー出身のアドバイザーに自宅から簡単に相談できる「無料オンライン相談サービス」がおすすめ!
▷家づくりのとびらを始める(無料)